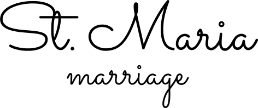宝石の爪留め・石留め方法の色々
|
目次 1.爪留め 2.玉留め 3.伏せ留め 4.フクリン留め 5.チョコ留め 6.共有留め 7.彫り留め |
さて今日は、宝石の爪留めや、その他の宝石の石留め方法の種類について、ご紹介します。
宝石の石留め方法には、「爪留め(ツメドメ)」「玉留め(タマドメ)」「伏せ留め(フセドメ)」「フクリン留め」等々、沢山の石留方法があります。
ぜひ、結婚指輪や婚約指輪等、ジュエリーをオーダーメイドする時の参考にしてみてください。

石留め一つで指輪の印象は大きく変わってきますので重要な要素です
1.爪留め
宝石を留めていく時に用いられる、最もポピュラーな石留めの方法が、「爪留め(ツメドメ)」です。

爪留めの婚約指輪
婚約指輪(エンゲージリング)では、特に爪留めをしたものがほとんどです。
この爪留めとは、台座と爪とからできている石座(シャトンとも呼ぶ)を作り、爪を倒して宝石を留めていきます。
台座とは宝石を乗せるための金属部分を指し、爪とは線状の金属部分の事を指します。
宝石の形にぴったりと合うように爪をカットしたうえで、タガネやヤットコと呼ばれる工具で、爪を倒して石を留めていきます。
宝石の大きさや形が、台座の大きさや爪の長さにぴったり合う事で、しっかりとした石留めをすることが可能になります。
それなので、あらかじめ宝石の形に合わせて、石座を作っておくことが重要です。
宝石を留める爪の本数は、2本、3本、4本、5本、6本、またはそれ以上と特に決まりはありませんが、婚約指輪の場合には、爪の数は4本、6本が主流になっています。
数本の爪が、石に対してそれぞれ均等に力が加わる必要があります。

センターは6本爪・その周りは3本爪・左右のダイヤは4本爪で石留めした婚約指輪
また爪をたおしていく時の力加減はとても重要です。
留めがあまいと宝石がカタカタと揺れたり、強すぎると石が割れてしまう事もあり得ます。
この爪の先端が、程よく宝石に密着している事が、洋服等に引っかかることのない使いやすい指輪になります。
また下記のように、6本の爪で、爪と爪との間が空く形は、光を取り込みやすく、ダイヤモンドの魅力を最大限に引き出してくれるため、とても人気がありますが、これもやはり「爪留め」です。
ちなみに、この台座の形状は、1886年にティファニー社が考案したもので、「ティファニーセッティング」や「ティファニー爪」と呼ばれ、130年以上経ても、なお婚約指輪の人気デザインになっています。

ティファニーセッティングと呼ばれている6本爪の「爪留め」
また、爪留めする時の、爪の先端の形(地金の形状)にも色々な種類があり、「剣爪」「鬼爪」「わし爪」「丸爪」「丸線爪」等々、それぞれに名称が付いています。
それらの爪の形状の名称については、以前「指輪の各部位の名称と役割について」のブログで、図を交え詳しく書きましたので、そちらもぜひ、併せてご覧ください。
2.玉留め
玉留めとは、「爪」と呼ばれる地金を立てずに、地金にダイヤモンドの大きさに合わせた下穴を開け、下穴に宝石をセットした後、魚子(ナナコ)タガネという工具で、地金を叩いて留めていく方法です。
3か所で留めていくのを3点留め、4か所で留めていくのを4点留め、と呼びますが、2点でもあるいは4点以上でも、留めることが可能です。
何点で留めるか、また留めていく位置によっても、指輪の印象が大きく変わります。
地金で爪を立ててはいないので、爪の出っ張りが無く、指輪の表側や内側に、誕生石などの宝石を埋め込みたいときにも、用いられるポピュラーな留め方です。

指輪内側に4点で玉留めしたルビーのアップ

結婚指輪内側に4点で玉留めしたルビー
3.伏せ留め
伏せ留めとは、宝石を留めたいところに、下穴を開け、そこに石をセットした後、石の周りの地金を全周に渡ってすべて、少しずつタガネで寄せて石留めする方法です。
石留後、寄せた地金部分を磨き仕上げれば、タガネを打ち付けた跡も分からなくなります。
4.フクリン留め
フクリン留めの多くは、カットの形状がカボションカット(半球状の表面がつるんとしたカット)と呼ばれている宝石を留める時に、多く用いられる留め方です。
(もちろん石表面がキラキラするようにカットされた、ファセットカットにも用いられてはいますが・・・。)

ダイヤモンドをフクリン留め
フクリンとは、漢字で書くと「覆輪」と書きます。
「覆輪」とは、もともとは、馬の鞍や甲冑(カッチュウ)等を金・銀・スズなどで縁どりして、飾ったり補強したものの事を言います。
「覆う輪」という漢字からイメージして頂けるかと思いますが、石の全周に地金で壁を作り、その壁を倒し留める留めていきます。
加工方法としては地金をパイプ状の形につくり、パイプの中に石をセッティングし石留していきます。
石の全周が若干地金で覆われますので、爪留めと比べると宝石が実際の大きさより、極若干小さく感じられてしまいます。
ですが、引っ掛かりが一切無く、指輪として非常に使いやすい石留方法になります。
5.チョコ留め
チョコ留めとは、地金を宝石の大きさに下穴を開けた後、石が入っている穴の淵を一周押しつぶすように留めていく石留方法です。
石の周りに斜めに照り返しと呼ばれる輝く溝が斜めに入るので、石が大きく感じられるのが特徴です。
チョコ留めは、「はめ殺し」「皿留め」「オーストラリア留め」などと呼ばれる事もあります。
6.共有留め
共有留めとは、文字通り2つの石を一緒同時に留めていく方法です。
石と石の間に爪を立て、爪を押しつぶすように留めていきます。

共有爪
共有留めした、エタニティ―リング「Riverbero]は、こちら
また、石畳を意味する「パヴェ」と呼ばれている石の留め方をする時にも、この石留め方法が用いられています。
また、この「パヴェ」で留められている指輪は、「パヴェリング」とも呼ばれています。
7.彫り留め
彫り留めとは、先端が彫刻刀のように彫ることが出来るタガネを使い、石の周りを彫ることで浮き上がった地金を爪として使い、宝石を留めていく留め方です。
彫り方によって、「五光留め」「マス留め」「レモン留め」等々、
色々な彫り方にも名前が付いています。

五光留め

マス留め
今回のブログでは、宝石の爪留めや、その他の色々な石留の方法についてや、その名称を詳しく書いてみました。
もしも、結婚指輪や婚約指輪、その他ジュエリーをオーダーメイドする時に、これらの名称まで分からなくても、もちろんオーダーして頂けます。
ただ、石留めの色々な方法を知っておくことで、デザインを考える時の巾も、広がるのではないでしょうか?
ぜひ、こういう石留めも参考にしながら、オーダーメイドを楽しんでいただければ幸いです。
St.Mariaでは、これらの石留方法のサンプルも、たくさんご用意していますので、
ぜひそちらのサンプルもご覧いただきながら、お好きな石留方法をご相談ください。
________________
結婚指輪・婚約指輪・オーダーメイド
St.Maria(サンタマリア)
*一組様ごとの予約制
*専用駐車場有
*ジュエリー全般制作可
東京都江戸川区北小岩8-11-11
OPEN:10:00~19:00(火曜休)
TEL: 03-5876-7030
MAIL:お問い合わせはこちらから
________________